ニューフェースたち



 園芸歴だけは古いけど、二年程前までは、私はいわゆる普通の園芸種しか育てたことがなかったんだよね。
園芸歴だけは古いけど、二年程前までは、私はいわゆる普通の園芸種しか育てたことがなかったんだよね。
primroseさんもどちらかというと今までは普通の園芸種を育てられるlことが多かったようですね。
山野草といわれる花たちの種まきを始めたのは、やっぱりsystemさんの影響が大きいかなぁ。
山歩きをしていても、山の花は山で見るのがいちばんと思っていたし、環境の違う平野部で育てるのは、どちらかと言えば邪道のような気もしていた。
2003年早春にsystemさんがセツブンソウの種を送ってくださって、いきなり私にとって初の山野草栽培が始まった。
種まきは小学校の頃からしていたけど、普通の花の種は特殊なものを除いてはたいていは2週間ほどで発芽する(と思っていた)。ところがどっこい、セツブンソウは種自体は大きくて問題ないけど、播種後一年経ってようやく発芽すると言う、気の遠くなるような話。しかも花が咲くのはまたそれから3年後、4年後だという。用土もそれまでは培養土、ピートモス、バーミキュライト、赤玉ぐらいしか使ったことがなかった。指導されたようになんとか鹿沼土や赤玉土、ピートモスを混ぜて播いてみたものの、一年間適度に湿り気を保ったままおいておくというのが、なんとも難しく、翌2004年春は見事に失敗。何にも出てこなかった(^^;)
また、その前年に種まきしたポレモニウムも、折角、夏前までには葉がよく繁っていたのに、7月の高温多湿であえなく駄目になった。
やはり用土が大事なんだね。培養土みたいな用土では夏は蒸れてしまって、高山系の植物は生き残れない。
そこで、今年からは山野草系や蒸れに弱いものは日向軽石や硬質鹿沼、ピートを適当に混ぜて植えている。そうしたら、36℃という猛暑でもなんとか少しは生き残ってくれたね。カラフトハナシノブなんていう、聞いただけでとても駄目っぽい花も真夏に咲いたんだよ。
ようやく少しだけ、なんかわかってきたかなぁというところです。
今年の秋はフウリンオダマキやイトシャジン、リシリヒナゲシなど、今まで発芽させたことのないものも何種類も発芽してるよ。
なんとか開花までこぎつけられたらラッキーなんだけど。
さて、春が来るのが楽しみなような怖いような。
画像は右からsystemさん由来の種からのキクバクワガタの少し大きくなった芽。
primroseさんにいただいた種からのヤナギバチョウジソウ。
Uniwiseの種からのカナリークリーパー、成長が旺盛でびっくり。
今日の陽射しを浴びてきらきらと光るダイアモンドリリー。




















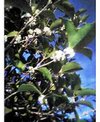


最近のコメント